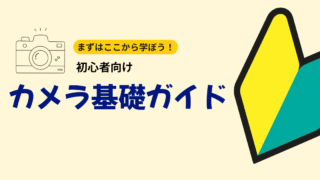【完全版】ホワイトバランスとは|見たままの色で撮れない悩みを解決!
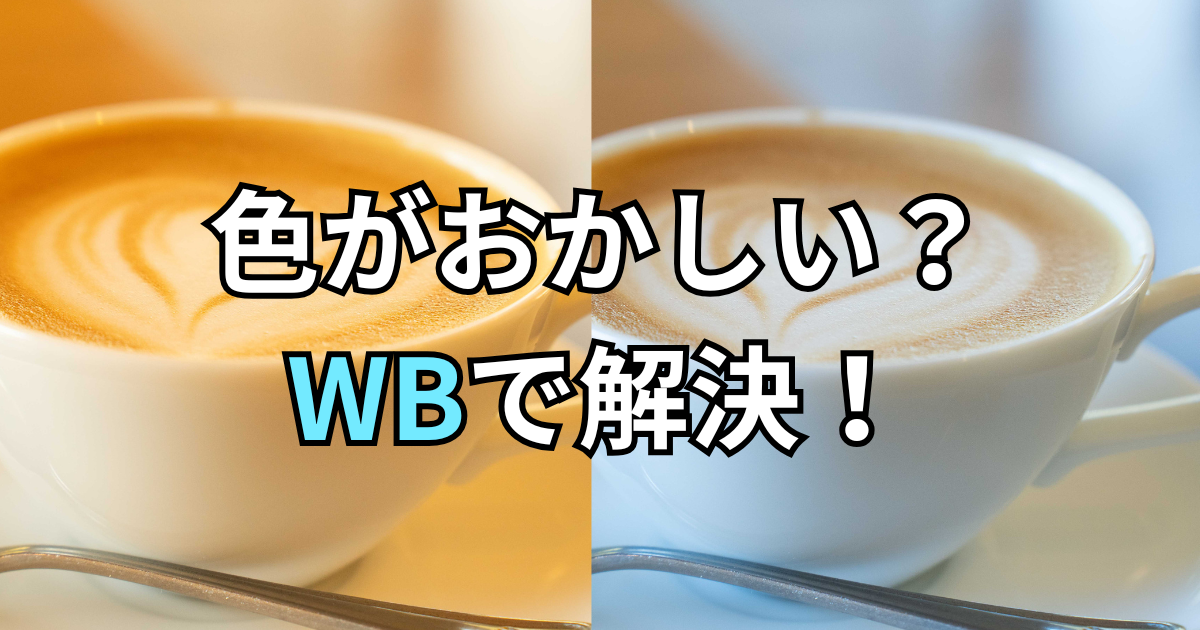
「せっかく料理を撮ったのに黄色っぽくて美味しそうに見えない」
「カフェで撮った写真が青白くて雰囲気が台無し」
「肉眼では綺麗だったのに、写真だと色が違う」
こんな経験はありませんか?
その原因は ホワイトバランス(WB) にあります。
この記事では、ホワイトバランスの基本からシーン別の使い分け、さらに雰囲気を演出する応用法までをわかりやすく解説します。
ホワイトバランスとは?
ホワイトバランスとは、光の色を打ち消して「白を白く」写すための機能です。
▪️曇り空の下では青っぽい光 → WB「曇り」で黄色を足して中和
▪️白熱電球の下ではオレンジっぽい光 → WB「電球」で青みを足して中和

ポイントは「光の色に反対の色を加えて中和、補正する」という考え方です。
👉 写真の基礎知識は他にもあります。
ISO感度の基本と使い方 や 絞り(F値)の基本、シャッタースピードの基本と並んで、ホワイトバランスも基礎の1つとしてとても重要です。
よくある失敗:室内で料理やカフェを撮ると黄色っぽい
これってよくありませんか?
▪️原因:室内の電球のオレンジ色に引っ張られ、料理全体が黄色く写る
▪️対策:WBを「白熱電球」に変更すると、黄色に反対色の青が加わり中和される。結果的に、料理や食器の色味が自然に表現される
WBを正しく設定すると、こう変わります👇


色温度という考え方
光の色は、色温度(いろおんど) という数値で表すことができます。
▪️数値が低い(2000K前後) → ろうそくや電球のようにオレンジ色っぽい
▪️数値が高い(7000K前後) → 曇り空や日陰のように青色っぽい
つまり、光源ごとに色温度が違うから、写真の色も変わってしまうのです。
図解:光の色温度とホワイトバランスの関係
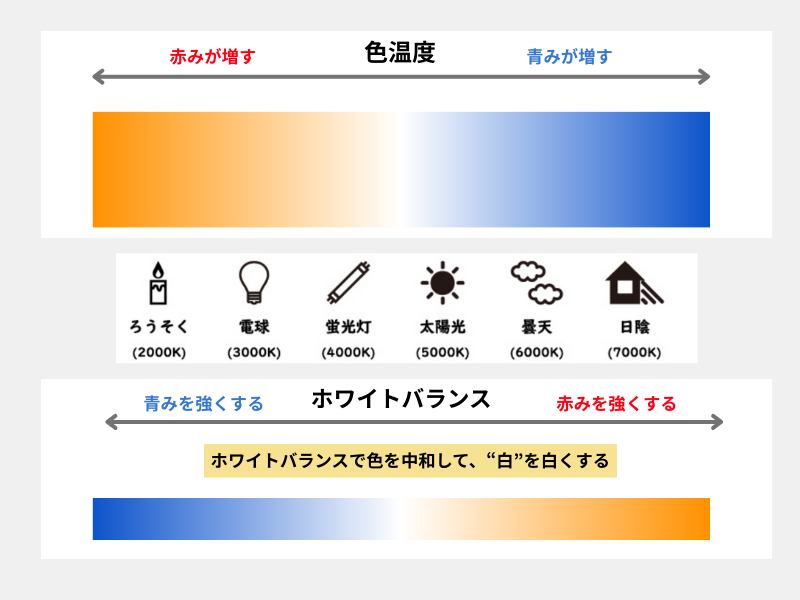
例えば「曇り空(6000K前後)」は青っぽい光 → WB「曇り」では赤みを加えて白に近づけます。
「電球(3000K前後)」はオレンジの光 → WB「電球」では青みを加えて中和します

「光の色温度」と「WBの補正方向」をセットで理解すると、なぜ写真が青くなったり黄色くなったりするのか腑に落ちますね!
シーン別ホワイトバランスの使い方
よくある撮影シーンごとのおすすめ設定をお伝えします。環境によっては違う設定の方が良かったりするので、あくまで目安としてください。
☀️ 晴天・日中の屋外
▪️推奨設定:AWB or 晴天(5200K前後)
▪️空の青をしっかり出したいなら「晴天」固定がおすすめ
☁️ 曇りや日陰
▪️全体的に青っぽくなる⇨顔色や花が青白く写る
▪️推奨設定:曇天(6000K)、日陰(7000K前後)
▪️肌や花が自然で暖かみのある色に
💡 室内(白熱電球)
▪️光がオレンジっぽい → 写真が黄色かぶり
▪️推奨設定:電球(3000K前後)
▪️料理やカフェ写真で効果大
🌆 夜景・街灯
▪️AWBだと黄かぶりが目立つことも
▪️推奨設定:電球 or 3500K前後に調整
▪️ネオンや街灯を自然に見せつつ雰囲気も出せる
応用編:ホワイトバランスで写真の雰囲気を変える
実はホワイトバランスは補正だけでなく、表現の道具としても使えます。あえて色被りを起こして雰囲気を変えることもできます。
青寄りに残す(低K値側)
青色を加える「電球」や「蛍光灯」にあえて変更することで、冷たい空気感、冬の透明感、夜の静けさを強調できたり、クールな雰囲気に変えることができます。
特に都市夜景で使うとカッコよくできます!


オレンジ寄りに残す(高K値側)
あえて「雨天」や「晴天」にすることで、オレンジ色を写真に加えます。温かみ、夕暮れのノスタルジー、カフェの居心地の良さを演出できます。
元々オレンジぽい夕焼けに、さらに黄色を足すことで夕焼けを強調することも可能です!



RAWで撮っておけば、後から自由にWBを変更できますよ!理想のイメージに合わせてWBを変更してみよう!
その他基礎を学びたい人はこちら
初心者がまず知るべき内容を一覧にしています。こちらを学ぶだけでワンランク上の撮影ができるようになります。
まとめ
✅写真の色が不自然になる原因は「光の色」=色温度
✅ホワイトバランスはその反対色を加えて中和する仕組み
✅シーンごとに設定を変えれば、スマホ以上に自然な色が表現できる
✅応用すれば雰囲気作りにも活用可能