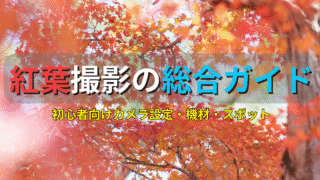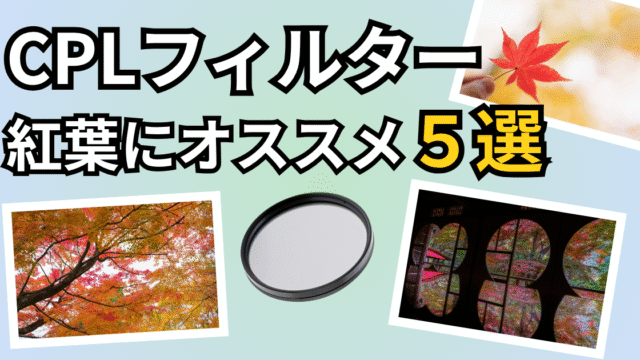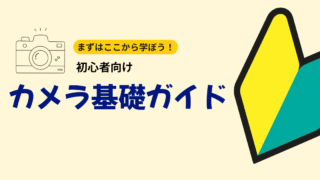紅葉撮影におすすめのレンズ10選【焦点距離別・マクロレンズ】

紅葉を撮るとき、”どのレンズを使うか(焦点距離の選び方)“で仕上がりは大きく変わります。
広角でスケール感を出すのか、標準で見たままを残すのか、望遠で圧縮効果やボケを楽しむのか。
ただ、レンズの種類は数え切れないほどあります。そこでこの記事では、紅葉撮影に特に相性の良い10本を厳選しました。
もっと多くの選択肢はありますが、初中級者でも選びやすいように価格帯・用途を考慮して絞り込んでいます!

実際に筆者が使ったことあるものばかりです。リアルな使用感や思ったことをお伝えします!
広角レンズ(16〜24mm前後)|紅葉をダイナミックに切り取る



紅葉のトンネル、リフレクションや境内全体をダイナミックに写したいなら広角レンズが活躍します。
16mm前後の広角なら、頭上の紅葉を含めて包み込むような構図が可能。観光地で混雑していても、被写体との距離を工夫すれば「人を小さく入れ、紅葉のスケール感を強調」できます。
また、広角特有のパースを活かせば、参道の奥行きや紅葉の並木道がよりドラマチックに。目で見た以上の臨場感を写真で表現できるのがメリットです。
✅風景として切り取る場合は、F4通しや暗めのF値でもOK
✅夜間に使用する場合は明るめのF1.8や2.8のレンズが最適
✅16-24mmをカバーしているものが使いやすい
Tamron 17-28mm F2.8 Di lll RXD|コスパ重視の広角ズーム
軽量・コンパクトながら開放F2.8で明るく撮れる、旅行や散策に最適な広角ズーム。
超広角を始めるにあたって、特に使いやすい焦点域をカバーしています。神社仏閣と紅葉を一緒に撮るなら20mmでも狭いと思うシーンが多いため、「17mmまで使えてよかった」と思おうことも多かったです。
価格も比較的手頃で、初めて紅葉撮影に挑戦する方にもおすすめです。中古なら6〜7万円で購入可能。
ソニーEマウント専用ですが、他メーカー純正にも似た焦点距離の広角ズームがあります。
| 焦点距離 | 17-28mm |
|---|---|
| 開放F値 | F2.8 |
| 重量 | 420g |
| サイズ | φ73×99mm |
| フィルター径 | 67mm |
| 最短撮影距離 | 0.19m |
| 手ぶれ補正 | なし |
| 発売年 | 2019年 |
Sony FE 20mm F1.8 G|紅葉と夜景に使いやすい広角単焦点
高い描写力と美しいボケが魅力の大口径単焦点。
紅葉の広がりを切り取りつつ、ライトアップでは玉ボケを背景に取り入れて幻想的に表現できます。
小型軽量で取り回しが楽なのも魅力。夜の紅葉リフレクション撮影にもぴったりです。手持ちで夜景x紅葉を綺麗に撮るなら、明るい単焦点を1つ持っておくと便利です。
| 焦点距離 | 20mm |
|---|---|
| 開放F値 | F1.8 |
| 重量 | 373g |
| サイズ | φ73.5×84.7mm |
| フィルター径 | 67mm |
| 最短撮影距離 | 0.19m |
| 手ぶれ補正 | なし |
| 発売年 | 2020年 |
Sigma 10-18mm F2.8 DC DN|APS-C用のコスパレンズ
世界最小・最軽量クラスのF2.8通し超広角ズーム。APS-C専用ながら描写はシャープで、建築物や紅葉トンネルなどの広がりをダイナミックに表現できます。
最短撮影距離がわずか11.6cmと非常に短く、前ボケを活かした超接近構図も可能。
紅葉を見上げたり、地面の落ち葉を主題に広がる木々を背景に入れたりと、スケール感のある紅葉風景を1本で作れるレンズです。
軽量なので登山やハイキングでの紅葉撮影にも最適。
| 焦点距離 | 10-18mm(APS-C専用) |
| 開放F値 | F2.8 |
| 重量 | 260g |
| サイズ | φ72.2×64.0mm |
| フィルター径 | 67mm |
| 最短撮影距離 | 11.6cm |
| 手ぶれ補正 | なし(ボディ内補正対応) |
| 発売年 | 2023年 |
標準レンズ(35〜50mm前後)|自然な視点で紅葉を残す




標準レンズは、人の目で見た景色に近い自然なパースで紅葉を写せるのが特徴です。
肉眼で感じたままの距離感や奥行きを再現しやすく、構図づくりの自由度も高い焦点距離です。
単焦点(35mm・50mm)なら開放F値が明るく、背景をふんわりぼかして印象的に仕上げるのに向いています。木漏れ日を背景に、1枚の葉を主題にした撮影やポートレートにもぴったりです。
一方で、24-70mmなどの標準ズームなら、被写体との距離を変えながら構図を探れるのが強み。紅葉トンネルの奥行きを出したり、人を入れたスナップにも使いやすい万能レンジです。
✅ポートレートや紅葉の切り取りなら明るめのF1.8-2.8のレンズが最適
✅何でも撮りたい場合は、F2.8やF4通しのズームレンズが便利
✅気軽にスナップ感覚で撮るなら、35mmか50mmの単焦点
Tamron 28-75mm F2.8 Di III VXD G2|万能標準ズーム
各社マウントに対応する定番ズーム。価格と性能のバランスが良く、紅葉散策に万能。
AFは速くストレスフリーで、解像感も十分。コスパ最強の標準ズームレンズです。普通の撮影において、このレンズで困るシーンはほぼありません。
解放の望遠端を使えば、背景のボケた紅葉やポートレートに。広角側では絞って紅葉の風景を綺麗に撮影できます。
私自身、キットレンズからこちらに乗り換えた経験があり、初めてのF2.8通しレンズにオススメです!
| 焦点距離 | 28-75mm |
|---|---|
| 開放F値 | F2.8 |
| 重量 | 540g |
| サイズ | φ75.8×117.6mm |
| フィルター径 | 67mm |
| 最短撮影距離 | 0.18m(広角端) |
| 手ぶれ補正 | なし |
| 発売年 | 2021年 |
Sony FE 55mm F1.8 ZA|ポートレート入門の単焦点
ポートレート入門として定番の単焦点。Zeissらしい透明感のある色味が特徴です。
280gと軽量ながら描写力が高く、紅葉ポートレートや紅葉の葉を主役にして背景に玉ボケを作るのに最適。
コンパクトなので他のレンズと併用もしやすく、鞄に忍ばせておくと便利です。
| 焦点距離 | 55mm |
|---|---|
| 開放F値 | F1.8 |
| 重量 | 281g |
| サイズ | φ64.4×70.5mm |
| フィルター径 | 49mm |
| 最短撮影距離 | 0.5m |
| 手ぶれ補正 | なし |
| 発売年 | 2013年 |
Sigma 18-50mm F2.8 DC DN|APS-C用のコスパレンズ
APS-C専用ながら、F2.8通し・軽量コンパクトを両立した万能標準ズーム。
換算27-75mm相当で、スナップ的な距離感から風景的構図までを自然にカバーします。
開放で撮れば柔らかなボケ感が得られ、背景を少しぼかした紅葉ポートレートにも最適。
紅葉の色づきを“目で見た印象のまま”に残したい人にぴったりのバランス型レンズです。
旅行や街中の紅葉スポットでも取り回しがよく、軽快な撮影スタイルを実現します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 焦点距離 | 18-50mm(APS-C専用) |
| 開放F値 | F2.8 |
| 重量 | 290g |
| サイズ | φ65.4×74.5mm |
| フィルター径 | 55mm |
| 最短撮影距離 | 12.1cm(広角端) |
| 手ぶれ補正 | なし(ボディ内補正対応) |
| 発売年 | 2021年 |
望遠レンズ(70〜135mm前後)|圧縮効果とボケで紅葉をドラマチックに



人混みの多い有名スポットでは、望遠レンズが最も頼れる存在。
神社仏閣の参道など、人を避けながら紅葉だけを切り抜けるのが望遠の真骨頂です。
さらに背景を大きくぼかして被写体を浮かび上がらせるのも得意。遠くの紅葉を前ボケに入れるだけで、肉眼では得られない立体感と奥行きを演出できます。
✅圧縮効果を活かすなら135mm-200mmをカバーしているレンズが最適
✅風景も紅葉の切り取りもしたいなら、70-200mm相当のズームが便利
✅ボケ感が欲しいならF1.8-4をカバーしてるものを選ぶ
Tamron 70-180mm F2.8 Di III VXD|軽量望遠ズーム
軽量ながらF2.8通しのコスパ最強望遠ズーム。同クラスの純正レンズの半額以下で入手でき、コスパ抜群。
紅葉を切り取るならF2.8以下の明るさでボケや玉ボケを綺麗に表現可能。携帯性とF2.8によるボケを楽しみたいならこれを買っておいて損はないです。
個人的には200mmと180mmの違いはほとんど気にならず、十分満足できる焦点域です。
手ぶれ補正がありませんが、大体のボディにはボディ内手ブレ補正があるので気になりません。どうしても必要な場合は第二世代のG2レンズを選択しましょう!
| 焦点距離 | 70-180mm |
|---|---|
| 開放F値 | F2.8 |
| 重量 | 810g |
| サイズ | φ81×149mm |
| フィルター径 | 67mm |
| 最短撮影距離 | 0.85m(全域) |
| 手ぶれ補正 | なし |
| 発売年 | 2020年 |
Sony FE 135mm F1.8 GM|紅葉ポートレートの最強単焦点
圧倒的なボケと解像感で、紅葉ポートレートの最強レンズ。ソニー純正レンズの中でも個人的にTOP3に入ります。
最短撮影距離が70cmと短く、被写体を大きく写せるので花や葉のクローズアップにも向きます。背景に光源があれば綺麗な玉ボケになり、幻想的な雰囲気を演出可能。
このレンズで紅葉を切り取ると、今まで撮ったどの写真よりも素晴らしいものが出てきます。
重量は950gと重めですが、このレンズでしか撮れない写真があるためデメリットには感じにくいです。
| 焦点距離 | 135mm |
|---|---|
| 開放F値 | F1.8 |
| 重量 | 950g |
| サイズ | φ89.5×127mm |
| フィルター径 | 82mm |
| 最短撮影距離 | 0.7m |
| 手ぶれ補正 | なし |
| 発売年 | 2019年 |
Tamron 50-300mm F4.5-6.3 Di III VC VXD|万能望遠ズーム
50mmから300mmまでをカバーする、圧巻の焦点距離レンジを誇る望遠ズーム。
広角端ではスナップ的な中望遠表現、望遠端では遠くの紅葉を圧縮して切り取る構図まで対応。軽量ボディと光学式VC(手ぶれ補正)により、手持ちでも安定したシャープな描写が可能です。
遠くの山肌に点在する紅葉など、風景として紅葉を切り取るなら最適のレンズ。F値は控えめですが、300mmで撮ればしっかりと背景もボケてくれます。
1本で“引きから寄りまで”秋の情景を自在に切り取れる汎用性の高さが魅力です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 焦点距離 | 50-300mm |
| 開放F値 | F4.5-6.3 |
| 重量 | 約665g |
| サイズ | φ78×150mm |
| フィルター径 | 67mm |
| 最短撮影距離 | 22cm(広角端)/90cm(望遠端) |
| 手ぶれ補正 | 光学式VC搭載 |
| 発売年 | 2024年 |
マクロレンズ|紅葉のディテールを切り取る
葉脈や水滴をクローズアップして撮りたい方にはマクロレンズがおすすめです。
CPLフィルターと組み合わせると反射が抑えられ、色彩がより鮮やかに浮かび上がります。
SIGMA 105mm F2.8 DG DN Macro|中望遠マクロ
中望遠の105mmマクロ。被写体との距離を取りやすく、背景を大きくぼかせるのが特徴。
紅葉の細部を切り取り、立体感ある写真を撮るのに適しています。
マクロレンズ特有でフォーカスはやや遅めですが、通常の撮影には支障のないレベルです。
やや長めの鏡筒で、設計も古めなためボディとのバランスは少し悪い点があります。
個人的には90mmマクロよりも105mmの方が圧縮効果が強く、ワーキングディスタンスも広いため、撮影範囲の自由度が増す印象です。
| 焦点距離 | 105mm |
|---|---|
| 開放F値 | F2.8 |
| 重量 | 715g |
| サイズ | φ74×133.6mm |
| フィルター径 | 62mm |
| 最短撮影距離 | 0.295m |
| 手ぶれ補正 | なし |
| 発売年 | 2020年 |
高額商品はレンタルも検討しよう
紅葉撮影におすすめのレンズを紹介しましたが、中には高額でなかなか手が出しづらいモデルもあります。そんなときは レンタルサービス を利用するのがおすすめです。
とくに Goopass は月額制のサブスク型レンタルで、使いたいときだけレンズを借りられます。旅行や紅葉シーズンなど限られた期間だけ使いたい方には最適なサービスです。

まとめ:紅葉撮影に最適なレンズを選ぼう
紅葉撮影では、焦点距離によって表現できる世界が大きく変わります。
✅広角ならダイナミックに風景全体、
✅標準なら人の視点に近い自然な距離感
✅望遠なら圧縮効果で奥行きを強調
どのレンズを選ぶかで、同じ紅葉でもまったく違う印象に仕上がります。
今回紹介した10本は、価格・描写・使い勝手のバランスを考え、初心者から上級者まで満足できるラインナップです。
あなたの撮影スタイルに合わせて、“この秋の1本”を見つけてみてください。
| 焦点距離 | レンズ名 | 特徴・おすすめポイント | 詳細リンク |
|---|---|---|---|
| 広角ズーム | Tamron 17-28mm F2.8 Di lll RXD | コスパの良い広角レンズ。明るいF値であらゆるシーンで活躍 | 詳細はこちら |
| 広角単焦点 | Sony FE 20mm F1.8 G | 夜間のリフレクションで手持ち撮影しやすい。 | 詳細はこちら |
| 広角ズーム | Sigma 10-18mm F2.8 DC DN | APS-C用の軽量コスパレンズ。16mm相当の画角でダイナミックに撮れる。 | 詳細はこちら |
| 標準ズーム | Tamron 28-75mm F2.8 Di III VXD G2 | コスパの良い標準ズーム。風景、スナップなどで活躍 | 詳細はこちら |
| 標準単焦点 | Sony FE 55mm F1.8 ZA | 紅葉xポートレートなどボケをメインにした撮影に最適 | 詳細はこちら |
| 標準ズーム | Sigma 18-50mm F2.8 DC DN | APS-C用の軽量モデル。28-75mm相当で風景やスナップにも最適。 | 詳細はこちら |
| 望遠ズーム | Tamron 70-180mm F2.8 Di III VXD | コスパの良い望遠ズーム。明るいF値で紅葉の切り取りやポートレートでも活躍 | 詳細はこちら |
| 望遠単焦点 | Sony FE 135mm F1.8 GM | 圧倒的な解像力とボケ。主題の切り取りやポートレートの最強レンズ | 詳細はこちら |
| 望遠ズーム | Tamron 50-300mm F4.5-6.3 Di III VC VXD | 使いやすい50mmから超望遠域まで。スナップや紅葉の切り抜きまであらゆるシーンをカバー。 | 詳細はこちら |
| マクロレンズ | SIGMA 105mm F2.8 DG DN Macro | 紅葉をマクロで撮影するのに最適。 | 詳細はこちら |