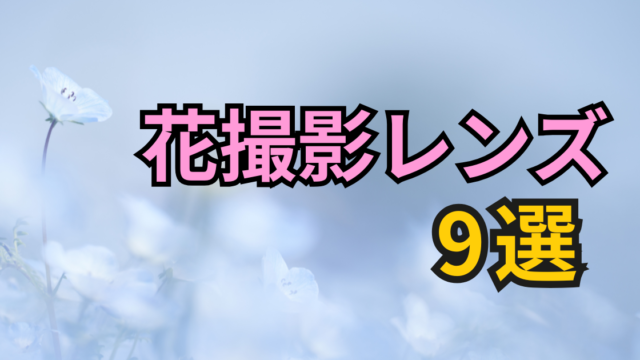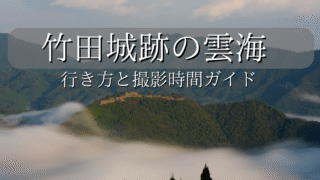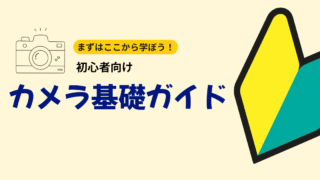FE 70-200mm F2.8 GM OSS II (SEL70200GM2) レビュー|風景撮影で感じた軽さと描写のバランス

風景撮影で中望遠〜望遠をカバーする代表的な一本。
今回はソニーの大三元望遠ズーム「FE 70-200mm F2.8 GM OSS II」を、風景撮影の視点からレビューします。
このレンズは、ポートレートやスポーツ向けという印象が強いですが、実際に風景で使ってみると「軽さ」「描写」「操作性」のバランスが絶妙。
旅先で持ち歩いても苦にならず、構図の自由度が高いレンズです。
主なスペック

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 焦点距離 | 70〜200mm |
| 開放F値 | F2.8 |
| レンズ構成 | 14群17枚(EDレンズ×2、スーパーED×2、XA×1) |
| 絞り羽根枚数 | 11枚(円形絞り) |
| 最短撮影距離 | 0.4m(ワイド端)〜0.82m(テレ端) |
| 最大撮影倍率 | 0.3倍 |
| フィルター径 | 77mm |
| サイズ・重量 | 約88×200mm/約1045g |
| 防塵防滴 | 対応 |
| 手ブレ補正 | 光学式(5軸ボディ補正対応) |
| その他 | 絞りリング搭載/インナーズーム構造/テレコン対応 |
デザインと操作性
第一印象は、とにかく軽い。
初代よりも大幅に軽量化されていて、手に持った瞬間に「これなら気軽に旅行にも持って行ける」と思いました。
見た目はしっかり白レンズで高級感がありますが、実際の使用感は驚くほど軽快です。
ズームリング・ピントリング
リングのトルクはどれも滑らかで、ピントリング・ズームリングともに適度な抵抗感があります。
ボディ側がズームリングになっている点も好印象で、ピントを触ってしまう誤操作を防げるのが個人的に気に入っています。
他社製レンズではボディ側がピントリング、先端がズームリングという構成が多く、少し扱いづらく感じることもあります。

絞りリングの搭載
絞りリングが搭載されているのも便利で、撮影中に手元で絞りを直感的に変えられるのは本当に快適です。
カメラを構えたまま左手で絞りを調整できるので、右手はシャッターに集中しながら、左手で表現をコントロールするような感覚で撮影できます。
風景撮影では光の変化が早いことも多いため、ダイヤル操作よりも絞りリングの方が素早く反応できるのも大きな利点です。

レンズフードの使いやすさ
小窓が設けられているため、CPLや可変式NDなどのフィルターを装着したままでも簡単に調整が可能。風景撮影ではCPLを使うことが多いので、フードを付けたままでも反射をコントロールできるのは助かります。
また、初代では花形フードでしたが、GM IIでは円形に変更され、レンズを床に置くときも安定しやすくなりました。レンズ交換時に仮置きする場面でも安心感があります。

なぜこのレンズを選んだのか
圧倒的な軽さ
このクラス最軽量の約1kgという軽さ。
風景撮影では三脚を使うことも多いですが、山道を歩いたり、日の出前に移動したりすることもあるので、少しでも軽い方がありがたい。また、旅行でも気軽に持って行けるのも高評価です。
ソニーのαボディはコンパクトなので、大きいレンズをつけるとどうしてもバランスが悪くなります。その点、この70-200mmはαボディとのバランスが良く、手持ちでも安定しています。

インナーズームという安心感
屋外での風景撮影では、ズーム時に鏡筒が伸びると埃や水滴が入りやすいですが、このレンズは内部でズームが完結するので安心。悪天候や霧の中でも、気にせず構図を変えられます。
FE 70-200mm F4 G IIも軽くて良いレンズですが、インナーズームではなく、絞りリングも非搭載。この操作感に慣れてしまうと、やっぱり絞りリングは必須になります。

目を見張る高画質
高画素機(α7R Vなど)を使っていると、レンズの描写力の違いがはっきり見えてきます。

タムロンやシグマの望遠ズームも使ったことがありますが、細部の解像感やコントラストの立ち上がりはGM IIが一枚上。
開放からしっかりシャープで、F8まで絞ると遠景のディテールまでくっきり描写してくれます。
所有欲をくすぐる外観
あとは単純に、GMバッジの存在そのものが所有感を満たしてくれます。

この赤いバッジを見るたびに「いい機材を使って撮っているな」と感じられるのは、やっぱりGMシリーズならでは。
ソニーユーザーにとって一つの憧れでもある存在で、撮影へのモチベーションを高めてくれます。
性能面だけでなく、持っていること自体に喜びを感じられるのも、このレンズの魅力のひとつです。
焦点距離の使い方と描写
風景を撮るときは、広角でスケール感を出すよりも「切り取る」ことが多いです。
峠から見る雲海や山並みも、70〜200mmがちょうどいい距離感。
70mmで全体を捉え、200mmで必要な部分を圧縮して引き寄せる。
被写体との距離を変えずに構図をコントロールできるのが、このレンズの強みです。


もし200mmで足りなければテレコンを装着して最大400mmまで使えるのもポイント。

F値は5.6になりますが、風景撮影では絞って撮ることが多いので全く問題ありません。
サードパーティ製ではテレコン非対応なため、この柔軟性がありません。
1本で70mmから400mmまで対応できるのは、現場では本当に便利です。
旅先でも使いやすい万能ズーム
このレンズを持っていれば、旅先でほとんどの風景をカバーできます。
例えば、季節の花を主題にしたカットも、70mmで風景に溶け込ませたり、200mmで花をふんわり切り取ったり。
開放F2.8では滑らかなボケも得られて、花や人物撮影、カフェでの撮影にもぴったりです。


旅先での風景撮影でも、この70-200mmという焦点距離は本当に使いやすい。
引いても寄っても対応できるので、その場の光や景色に合わせて柔軟に構図を変えられます。
広がりを残した風景も、遠くの山や花を切り取るようなシーンも、この1本でしっかり撮れる。いろんな場面で活躍してくれる、頼もしいレンズです。

他レンズとの使い分け
もちろん、ボケ量で言えば単焦点の135mmや85mmには及びません。
花やポートレートなど、テーマが明確なときは単焦点を使います。
ただ、構図を探りながら撮るようなときや、旅先で「何が撮れるかわからない」状況では、この70-200mmが最も安心できる。
70〜200mmの間で構図を調整できることで、撮影の幅が一気に広がります。

まとめ

FE 70-200mm F2.8 GM OSS IIは、風景撮影でも非常に完成度の高いレンズです。
軽く、取り回しやすく、描写も申し分ない。
ズームで構図を探しながら撮るスタイルの人にとっては、まさに理想的な一本。
荷物を減らしたいけど画質は妥協したくない、そんな人にはこのレンズを強くおすすめします。
実際に使ってみると、“持ち出す気になる70-200mm”という言葉がしっくりきます。
新品のレンズを検討するなら、SONY公式サイトが断然オススメ。デフォルトで3年のメーカー保証が付いてるため安心して購入・使用できます。

中古を検討するなら楽天市場がオススメ。ポイントアップ期間に購入すれば、思った以上に安く購入できる場合も。楽天のマップカメラやキタムラもあるため保証も安心です。
FE 70-200mm F2.8 GM OSS IIは本当に素晴らしいレンズですが、価格的には簡単に手を出しづらい部分もあります。
そんなときは、レンタルサービスをうまく活用するのもおすすめです。
とくに GooPass は月額制のサブスク型レンタルなので、使いたいときだけ気軽に借りられます。
旅行や紅葉シーズンなど、限られた期間だけこのクラスのレンズを試したい方にはぴったりです。
実際に撮影で使ってみると、重さや焦点距離の感覚など、カタログでは分からない部分をしっかり体験できます。